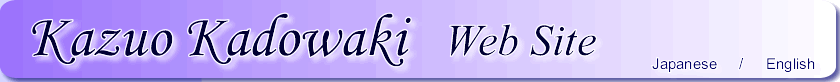|
筑波大学物質工学系教授 門脇和男
最近、国立大学の独立行政法人化(以後独法化と略す)の問題が様々な形で論議を呼んでいる。私が所属する筑波大学に於いても例外ではない。学長の説明会も行われ、独法化へ移行することが確実であることが伝えられた。それに先だって、図書館情報大学との合併がなされるという。
そもそも、話題の独法化とは何であろうか?特に“国立大学”における独法化とは何を意味するのであろうか?
議論が沸騰している独法化問題の発端が国の行政機関を整理し、公務員の定員を削減するという純粋に行政上の問題にあることは周知のことである。国立大学も国の行政機関である文部省の管轄にあるため独法化は避けられないという論理である。東京大学や京都大学の総長が正式に反対声明を出す理由はまずこの点にあるが、大学人としては至極当然のことに思える。しかし、実はそう生やさしい問題ではない。それは「“国立大学”とは何か」と問い詰めると、実は大変不思議な存在であることに気が付くからである。
そもそも国立大学とは明治から昭和初頭にかけて、我が国の国民教育水準の向上と欧米諸国の進んだ文化や科学技術を振興するために設立された7帝国大学が始まりである。第二次大戦後、それが大幅に拡大された。昭和24、25年生まれを頂点とするベビ−ブ−ムもあり、人口の急増がこれを加速し、私立大学も含め大学が倍増された。大学が急速に大衆化していく。このような時代の流れのなかで、国立大学は高等教育を担う国の学校として、また一方で、国立の学術研究機関として拡大され、現在では99校にも達している。
教員はすべて国家公務員であり、資金はすべて国の歳出である。このような状況は先進諸外国には無い制度であり、また、それ以上に問題と思われることは、現状の国立大学は私立、公立大学共存の中にあって、過去における帝国大学のような特殊事情が無くなったにもかかわらず依然そのまま存続し続けてきたことにある。こう考えると、なぜ国立大学でなければならないかという素朴な疑問に答えることができなくなってしまう。国立大学が今日まで存続していること自体が、我が国の行政の停滞を象徴しているかのように見えてくる。
ここで重要なことは、まず、独法化を離れて、現状の国立大学をどのようにしたらよいのかを原点から考え直すことが必要ではないだろうか。現状の文部省から切り離すことは必要不可欠であろうが、そうした場合、国立大学とは何を意味するのだろうか?独法化に際して国立大学を廃止し、すべてある種の私立大学にしてはどうかといった強硬論の所以である。いずれにしろ、大学の運転資金は業務内容から判断して国、民間、法人などから調達し、大学内部でその使途を決定し、大学間の特徴を生かし成果を競い合う形態が理想ではないだろうか。それに見合うだけの資金を国、法人、民間が多方面から多角的に資金供出を行うことが望まれる。ややもすれば、一極集中型の組織形態を本能的に指向する我が国の行政施策は、実は破滅的な結果をもたらすことは70-80年代の経済一極体制を見ても明らかであり、大学に於いてはなおさら致命的な結末を生むこと必至であるからである。過去50年間における科研費制度を忘れてはならない。独創性を大学に求めるなら独法化は当然であるが、緊縮財政のための合理化を求めるならむしろ独法化は必要ないであろう。大局的見地から抜本的な改革を行うべきであるが、昨今の偏重した大学重点化や文部省主導型の大学改革指導などは、見るからに矮小化した官僚と大学人の癒着と利己主義の現れであり、独法化の先行きに暗い陰を落としている。実力があれば独法化しても十分存続できるはずであろう。今、優位性を先行する必要はどこにあるのだろうか。日本人が日本人として存在する限り、たとえどんな地理的条件であろうとも総体としての知力は保存しているはずである。それを有効に発掘し、伸ばし、人類社会のために貢献できる構造を作るのが行政手腕であり、それを具現化すること自体が独法化の目指すところであろう。
(平成12年9月27日)
|